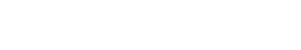ご注意
ゲーム本編の時間軸とは切り離した
特別編としてお楽しみください。
ゲーム本編の時間軸とは切り離した
特別編としてお楽しみください。
2025年スペシャル年賀SS 『素敵な一年のはじまり』
生徒会室では、年末恒例のとある行事が会議の議題に上っていた。
「年越しのパーティー、ですか?」
「ああ。冬休み、寮に残る生徒たちのために、生徒会主催で年越しパーティーを開催してるんだ」
私のような留学生や、実家が遠方で帰省が難しい生徒たちがいるので、そんな生徒たちのために講堂を貸し切ってパーティーを開くのが毎年の恒例なのだと会長は説明してくれた。
「わあ。なんだか楽しそうですね……!」
「へえ、生徒会ってそんなこともやってたんだな」
「えっ、イザヤも知らなかったの?」
「俺、通学生だし。生徒会に入ったのも今年からだしさ」
「あ……そういえばそうだよね」
「お前は家族と離れて年越しするの、初めてだろ? 寂しかったら家に来いよって声かけようと思ってたけど、ちょうど良かった」
そう言って、イザヤが私の頭をぽんと撫でて笑う。
アレクが明るい声で茶々をいれた。
「はいはい、彼女のひとりじめはダメだからね~?」
「へえ~。そういう発想が出てくるってことは、ひとりじめしたいのはアレクじゃないのか?」
「そりゃまあ、できるなら……。と、そういう話じゃなくて!」
「お前が振ったんだろうが」
「ま、まあとにかく、俺が言いたいのは皆で年越ししたほうが楽しいよねって話! ね? 君もそう思うでしょ?」
「うん! 皆と年越しできるなんて、嬉しいよ」
気遣うように、会長が皆の顔を見渡しながら付け足した。
「生徒会主催といっても、普段の学校行事と比べて大がかりな準備もないし、人手が要るものじゃない。メンバーの中で帰省したい者がいたら、遠慮なく言ってくれ」
その声に、テーブルの上のクッキーをつまんでいたリカルドとソファに寝そべっていたラルスが応じる。
「俺は参加する。家のほうはカシュの様子だけ見に行けば充分だからな」
「……俺も。はなから家に帰るつもりないし」
「ふふ、りっくんは料理目当てでしょ? おいしいものが食べられるならどんなイベントでも顔を出すよね」
「おいアレク、人を食い意地がはってるみたいに言うな。俺はただ、学校のほうが鍛練の設備が揃ってるから残るだけだ」
「でも、本当は~? この学校のコックが~?」
「ああ、この学校のコックは超一流の腕前だからな! 年越しパーティーの料理も何が出るか楽しみだ!」
「あはっ、やっぱりそっちが本音」
「い、今のはお前が言わせたんだろうがっ!」
軽口を叩き合っているふたりを呆れ顔で一瞥してから、グレースは私の腕にぎゅっと手を回した。
「もちろん私も参加するわ。親友とお兄様と一緒に年を越せるなんて、最高じゃない!」
「あっ……でもパーティーってことは、ドレスで参加するんだよね?」
私を安心させるように、コーヒーの湯気の向こうで会長が微笑んだ。
「パーティーといっても、気楽なものだからそう構えなくていい。他の生徒たちも皆、私服で参加するから安心してくれ」
その言葉にほっと胸を撫でおろしていると、グレースが小声で私の耳元に囁く。
「ねえ、この前いいお店を見つけたの。今度パーティーで着る服を買いに行きましょう?」
「わ、わざわざ? だって会長が構えなくていいって……」
「それはそれ、これはこれよ! せっかくのパーティーなんだからお洒落しなきゃ! ……そしてお兄様をどきりとさせて……ふふっ」
後半の内容については聞かなかったことにしようと思う。たしか建国祭の時もこんなやりとりをしたなと懐かしさを覚えてしまう。
年末は、てっきりひとりで寂しく年を越すものだと思っていたから、年越しパーティーという思いがけない話に嬉しさもひとしおだった。
「ふぁ……。アレクとリカルド、さっきからうるさい。睡眠の邪魔」
「おいラルス、寝るな! まだ会議中だぞ」
「ちゃんと議事録はとってるし、話は聞いてるから問題ない」
「って言ってるけど……どうなの会長?」
「はぁ……問題あるに決まってるだろう。ラルス、ちゃんと起きろ。会議を続けるぞ。では全員参加ということに決まったわけだが、当日の準備について――」
今年の年越しはにぎやかになりそうだ――
そんな期待を胸に、私は頬を緩めたのだった。
――そしていよいよ年越しパーティー当日の夜。
グレースと一緒に選んだ、リボンをあしらったケーブル編みのワンピースを着て、私はパーティーに参加していた。講堂には各寮に残っていた生徒たちが集まり、料理と会話を楽しんでいるようだ。
「ふふ、いいわね。やっぱり私が一緒に選んだだけあってそのワンピース、あなたによく似合ってるわ」
「これバルーンシープの羊毛ですごくあたたかいんだ。お気に入りの一着になったよ!」
周囲を見回すと皆も私服とはいえ、普段よりお洒落をしているみたいだ。
うきうきとした開放的な空気があたりに満ちていて、新しい年を皆で楽しく迎えたいという生徒たちの思いが伝わってくるようだった。
「あら、今日は一段と可愛いじゃない。さすが、私の一番の友達ね!」
肩を叩かれ、振り返るとそこにアニスが立っていた。
「ありがとう、アニスもすごく可愛いよ!」
「ねえ、あそこに生徒の写真を撮る係の人がいるの。一緒に撮ってもらわない?」
グレースがずいと前に出て、いつものお約束と言った感じでアニスに軽く笑いかける。
「あらアニス、そういうのは親友の私を通してもらわないと困るわね?」
「仕方ないわ。それじゃグレースも一緒でいいわよ?」
「ふふ、アニスもグレースも、皆で撮ってもらおうよ!」
ふたりともよく言い合いはするけれど、なんだかんだで仲が良い。この学校に来て、彼女たちの存在にどれだけ助けられただろう。
係の人に頼んで、3人並んで写真を撮ってもらう。良い記念になったと喜んでいると、アニスが急に声を潜めて、離れたテーブルを目線で指した。
「ねえ、ところで……あっちにあなたのことを恨めしそうに見てる子がいるんだけど、大丈夫?」
「あ……メアリーゼ……!?」
メアリーゼが少し離れた場所から、じっと私のほうを見ている。なにか用があるのだろうかと近づいていくと、彼女はまさかこっちに来るなんて、という驚いた顔をした。
「メアリーゼ、どうしたの?」
「べ、別に! あなたに用なんてありませんわ! ただ、その、この前のことで……」
「この前の? ああ、もしかして――」
冬休みに入る前、中庭で転んでしまったメアリーゼを見かけたので、手を貸して医務室に連れていってあげたのだ。
メアリーゼが言っているのはおそらくその時のことだろう。
「少し血が出てたけど、怪我は大丈夫だった?」
「ええ、かすり傷でしたからすっかり治りましたわ。それでその……あの時、応急手当てとしてハンカチを巻いていただいたでしょう? それを返さなければと思って……」
「ああ、それで……! あれ? ハンカチ、2枚あるけど……」
1枚は私がメアリーゼの応急手当てとして使った物。もう1枚は刺繍が施された高級そうなシルクのハンカチだ。
「こ、これは、別にお礼の気持ちなんかじゃありませんわよ! 貴族として当然の気遣いですわ!」
恥ずかしそうに顔をそらして、メアリーゼは足早に去っていってしまった。
もしかしたらずっと話しかけるタイミングを窺っていたのかもしれない。早く気が付いてあげれば良かったと思いながらグレースたちのいるテーブルに戻ると、そこに生徒会メンバーも勢ぞろいしていた。
アレクが私を見るなり、目を輝かせて笑う。
「わ、今夜の君、可愛くて心臓止まるかと思った……!」
「もう、大げさだよアレク」
「大げさじゃないよ。ねえ、りっくん、ラルス?」
アレクに呼ばれて、夢中でスペアリブを食べていたリカルドと、オスタラを抱えたラルスがこちらを振り返る。
「ああ、まあ。いいんじゃないか」
「……色合いが、魔法ヤギ種のマルネラゴートによく似てる」
このやりとり、やっぱり既視感がある。建国祭の時のあれだ。
ふたりともあの時と変わらないなと吹き出しそうになっていたら――
「……お前にしちゃ、よく似合ってるよ」
小さな声で呟いた、リカルドの柔らかな声音が耳に届く。
「えっ……。い、今なんて……」
「似合ってるって言ったんだ。に……二度も言わせるなっ……!」
あの女子の装いに興味のなさそうなリカルドが、今、似合ってると褒めてくれた……?
聞き間違いかとぱちぱち瞬きをしていると、続けてラルスがぼそりと言う。
「あんたは何着ても、あんただし。……可愛いか可愛くないかで言ったら、ま、可愛いんじゃない?」
「ええっ……。あ、あの、そんなに気を使わなくてもいいよ?」
「使ってない。思ったこと言っただけ」
そう言ってふいとラルスは私から視線をそらし、オスタラを撫でる。
リカルドもラルスも、何事もなかったかのように振る舞っているけれど、頬は少しだけ赤く染まっていた。
予想外の反応にこちらまで恥ずかしくなってきてしまう。
「あ……ありがとう……」
「ふふ、りっくんもラルスも、昔よりだいぶ素直になったよね~。彼女のおかげかな?」
「う、うるさい、いちいちからかうな!」
「……あれ? でもこれ、俺もうかうかしてるとまずい……? うーん……」
ふっと何かに気づいたような顔でアレクが呟く。
「うかうかってなんのこと? アレク」
「あー、いやいや、こっちの話!」
胸の前で軽く手を振ってから、アレクが私の頭のあたりに視線をやった。
「あ、髪飾りが少し曲がっちゃってるね。直していい?」
「う、うん」
私の背中に回り込むと、アレクはそっと髪飾りに手を伸ばす。彼の指先が髪に触れ、息づかいを間近に感じた。
「ふたりに負けてはいられないし……。もう少し、俺も素直にならないとかなぁ……」
「……どういう意味?」
「んー。どういう意味かっていうとね~」
息がかかるくらい耳元に顔を寄せ、アレクが囁く。
「……君には俺が言う『可愛い』が一番響いてほしいなって――」
一瞬、どきりとしたけれど彼はすぐに身体を離して、私の前に立つとにっこり微笑む。
「はい、これでよし! ちゃんと直ったよ」
「あ、ありが――」
お礼を言い終える前に、イザヤが私とアレクの間に割り込むように入ってきた。
「おい、そこ、ちょっとくっつきすぎじゃないか? 気が緩みすぎてるぞ第二王子」
「はいはい。ねえ……目が怖いってイザヤ」
アレクが苦笑しながら肩をすくめ、一歩退く。イザヤは私に向き直り、持っていたグラスを差し出した。
「ほら、ぶどうジュース。飲むか?」
「わ、ありがとうイザヤ。ちょうど喉が渇いてたんだ」
受け取ったぶどうジュースで喉を潤す。イザヤが言う通り、ほどよい甘さでとてもおいしい。
彼はそんな私を、目を細めて見つめていた。
「……どうしたの?」
「いや、こうしてお前と一緒に年を越せて良かったなって思って」
「ふふ、なに急に。変なイザヤ」
「すっかり生徒会の立派な一員になって、友達もたくさんできて……。お前が楽しそうにしてるの見ると、なんか嬉しくて、しみじみしちまって」
いつものように私の頭をぽんぽんと撫でてイザヤが笑う。
「それになんか最近、お前が眩しく感じてさ。急に大人っぽくなったっていうか、俺から離れていきそうで……寂しいっていうか……。って、あれ? なに言ってんだ俺――」
戸惑ったようにイザヤは顎に手をやると、声を強めた。
「ま、まあ、とにかく良かったってことだ! 今夜は楽しく過ごそうぜ」
「うん……!」
「イザヤ、ちょっと準備の確認、いい?」と、アレクに声をかけられ、「また後でな」と言うとイザヤはアレクと一緒に、リカルドたちのいるところへと歩いていく。
パーティーの準備は終わったはずだけど、なんのことだろう?
疑問に思いつつ、ふと空腹を感じて料理が並べられたテーブルへと視線を向けた。
色鮮やかなフルーツが盛られたお皿に、レイシがあるのを見つけて手を伸ばす。生徒たちで混雑していたので少し取りにくいなと思っていると、さっと会長がレイシを含めたフルーツをお皿にとって、私に渡してくれた。
「はい、どうぞ」
「わっ、会長……! ありがとうございます」
レイシを口に運ぶ私に、会長は穏やかな笑みを浮かべる。
「パーティーは楽しんでるか?」
「はい……! 会長はどうですか」
「ああ、すごく楽しい。……今年は君もいるしな」
会長は何気なく言っただけなのに、そんなに優しい声で言われると、鼓動が速くなってしまう。私は焦って口を開いた。
「わ、私……、こんなに賑やかな年越しは初めてです」
「それは良かった。この一年、楽しい思い出がたくさん作れたならいいんだが」
「ふふ、大変なこともあったけど、楽しいことばかりでした。もうサナン王国に帰りたくないって思ってしまうくらい……」
じわりと胸にあたたかな想いが溢れていく。この学校に留学して、友達ができて、生徒会の皆に会えて……本当に刺激的で幸せな一年だった。
「私、ずっと……この日のことも、皆と過ごした時間も、忘れません」
「……俺も忘れない。君が隣で笑っている、この瞬間を――」
まっすぐに見つめられて一瞬、心臓が跳ねる。
だけど会長はすぐにいつもの落ち着いた声で、講堂の時計を見て言った。
「ああ、そろそろ時間だな」
「えっ、時間……?」
生徒会メンバーのところまで歩いて行くと、会長は皆に声をかけた。
「皆、もうすぐ0時だ。例の準備はいいか」
「はーい、了解!」
「よっしゃ、やるか。おいラルス、こんなところで寝るな」
「ほんと、ぐうたら男なんだから」
「……ちゃんとやるって。オスタラはここで待ってて」
「それじゃ、各自、持ち場に移動しようぜ」
頷きを交わす彼らに、私は焦って問いかけた。
「ちょ、ちょっと待って、皆。準備ってなに? 私、聞いてないよ?」
「君にとって、今回が最初で最後のこの学校での年越しパーティーだろう? だから、少し趣向を凝らそうと思ってな」
「つまり、俺たちからのちょっとしたサプライズプレゼント! 受け取ってよ」
皆はそれぞれ、行き先が決まっているかのように駆け足でその場を去っていく。
いったい何が起きているのだろう――
呆然と立ち尽くしていると、会長の声があたりに響いた。
『今年も残りわずかとなった。皆、新しい年の幕開けを共に祝おう』
その言葉を合図に照明が徐々に落とされ、薄暗くなった講堂にカチ、コチ……と時計の秒針を刻む大きな音が鳴り渡る。
「なになに?」「何が起きるの?」と、なにか楽しいことが起きそうな予感に、生徒たちが目を輝かせてざわめきだす。
「5、4、3、2……」
会長がカウントゼロを告げ、魔法を詠唱する生徒会メンバーたちの声が聞こえたかと思うと――
講堂のあちこちで色とりどりの大きな光の花が咲き、どこからか巻き起こった柔らかな風に乗り、花びらやリボン、ラッピングされたクッキーやキャンディが天井からふわふわと降りそそぐ。
「わあっ……!」
生徒たちから歓声と、新年を祝う声が飛び交う。
なんて素敵なんだろう。そこかしこできらめく魔法に魅入っていると、いつの間にか皆が私の傍まで戻ってきていた。
「どうだ、俺たちのサプライズは! 最高だっただろう?」
「うん。最高だった! 皆、すごいよ……!」
興奮気味に頬を紅潮させるリカルドの隣で、「ま、そういうわけだから、今年もよろしくな」とイザヤが笑う。
その言葉をきっかけに、皆で口々に新年の挨拶を言い合った。
「新しい年もよろしくね~!」
「……よろしく」
「今年も親友らしいこと、たくさんしましょうね!」
「にゃー!」
「ふふ……。皆、新年もよろしくお願いします!」
軽くお辞儀して顔を上げると、会長と視線が合った。
「……今日のこの瞬間は、いい思い出になりそうか?」
「はい……! きっと私、この夜を一生忘れません……!」
会長がふわりと包み込むような優しい笑みを浮かべる。
素敵なサプライズと新年の始まりに胸をときめかせ、賑やかな夜は過ぎていった。
そして翌日――
私たちは講堂に集まり、途方に暮れていた。
「――ということで、皆、新年最初の仕事は、年越しパーティーの後片付けだ」
リボンや花びらがあちこちに散らばった講堂で、会長が静かに告げる。
「ねえちょっと、あんなところにまで花びらが落ちてるわよ」
「さすがにお菓子は皆、持って帰ったようだけど。まぁ……派手にやったよね」
「去年の倍は、掃除が大変そうだな……」
「まあいいじゃない、りっくん。彼女が喜んでくれたんだから! ねえ、イザヤ」
「ああ、片づけなんて皆で協力すればあっという間だ。今年のほうが人数だって多いだろ?」
皆に向かって、私は元気に声をあげた。
「私、準備は手伝えなかったから、その分、片づけを頑張るよ!」
勢いよく言う私を見て、イザヤがにやりと笑う。
「おっ、年明けから気合い充分だな。その意気だ」
「そうだ! だったら、誰が一番多く花びらとリボンを集められるか競争しないか?」
「も~。すぐりっくんは競争したがる~」
「最下位は食堂のアイス奢りだ!」と笑いながら、リカルドは駆けていく。「負けないよ!」と返して私も早速、掃除にとりかかった。
……ほら。掃除だってなんだって、皆と一緒ならどんなことも楽しいんだ。
今年も、素敵な年になる――きっと。
くすりと笑って、私は足元の花びらを拾い上げた。