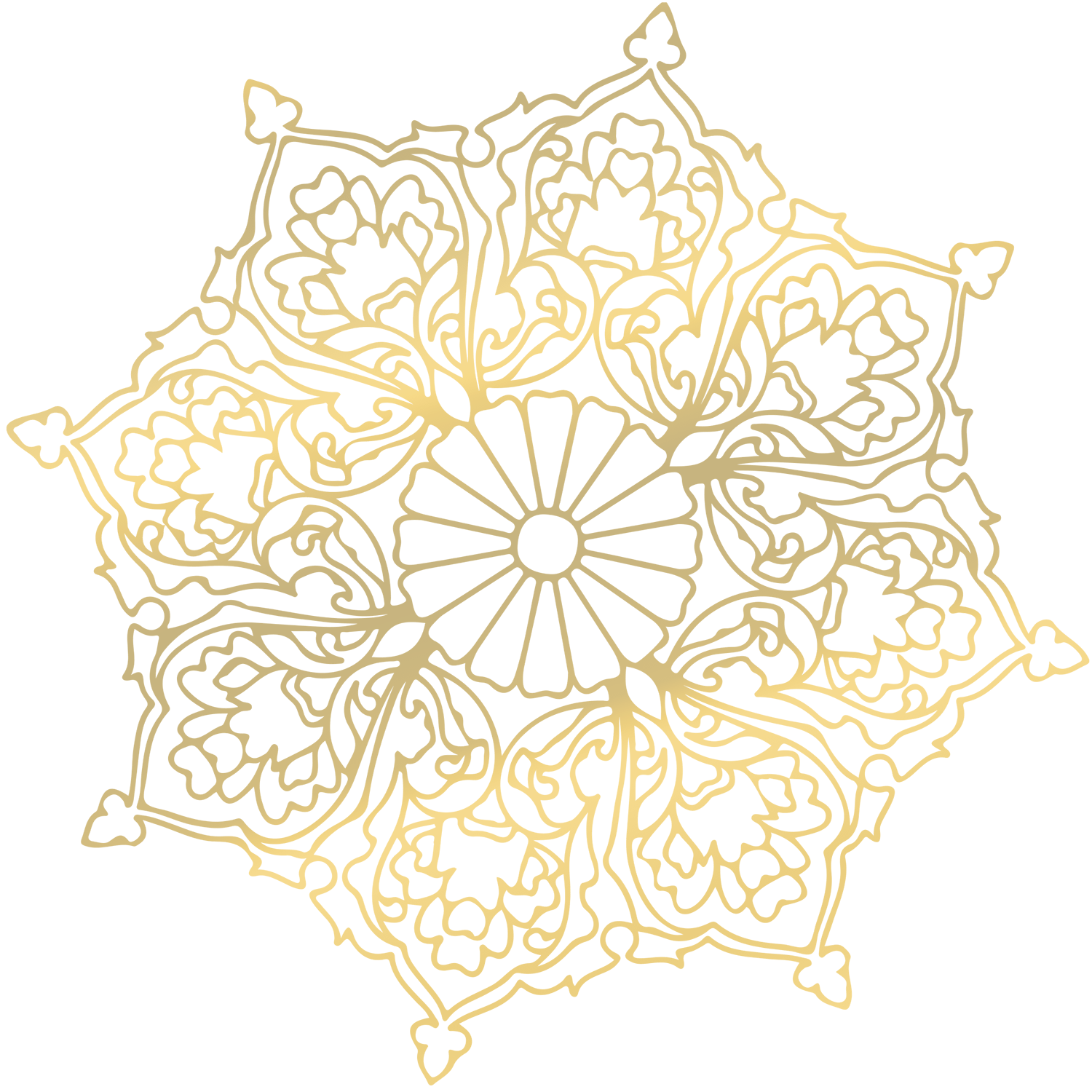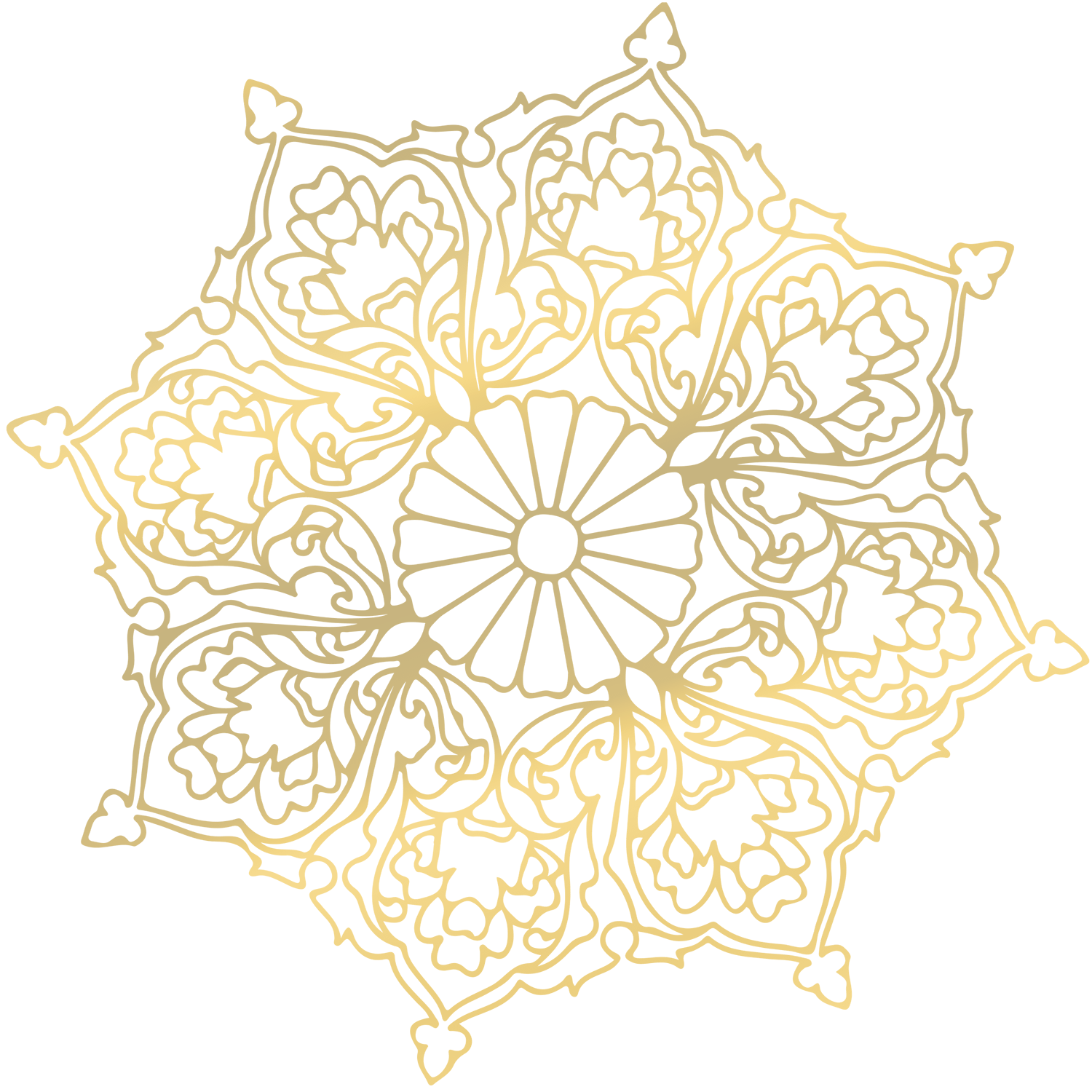Gallery

-
鱗 皇驪
「ああ、白娘子……。
そなたと……ずっと、こうしたいと願っておりました……」
-
囁いて、皇驪皇太子が私の喉に舌を這わせる。
――不意打ちで、ぞくりとした震えが走った。
-
シリーン
(これ……まさか……)
-
鱗 皇驪
「ああ……甘い……。
そなたの喉を伝う桃の雫は、なんて芳しいのでしょう……」
-
シリーン
(まさかこの人……私に桃を食べさせて興奮している……!?)
-
驚いたことに、皇驪皇太子はタトゥーの熱に当てられたというのに、私に桃を食べさせるだけだった。
-
シリーン
(っ、確かに……美味しい、けど――)
-
剥いた桃から、次々と果汁が滴り落ちていく。
彼の手も、私の喉も顎も、あっという間に甘い香りになっていった。
口を開いても、僅かに咀嚼できるだけ。
丸々と大きな桃を噛むのは難しく、私は桃を咥えるのに精一杯になっていた。
-
鱗 皇驪
「ああ……。どんどん落ちてきますね……。
こんなに熟れて……甘い……。
ん……」
-
シリーン
「……っ……」
-
無意識なのだろうか。扇情的に喉元を舐められて、声を上げそうになる。
けれども桃のせいで声は形にならない。
彼は、私の身体に一切手を出そうとしなかった。
あんなにも、目に欲望を湛えているのに。
ただ、私の喉や首筋を舐めるだけだ。
――どこまで屈折しているのだろう。
-
鱗 皇驪
「さあ……そなたも、桃を食べてください……甘くて、美味しいですから……」
-
シリーン
(っ……甘い……けど――)
-
懸命に少しずつ、桃を食べていく。
けれども、食べられる部分よりも垂れていく果汁のほうがずっと多い。
-
鱗 皇驪
「ああ……白娘子……。そなたの白い肌が、
こんなにも桃の雫で……ん……まるで、桃を食べているみたいです……」
-
シリーン
「っ……ん……」
-
私が桃を噛む音と、お互いの熱い息遣い。
時折、縛られている椅子が軋む音だけが静かな夜に響いていく。
悪いことなんて何もしていない。
そう思うのに何故だか、私は背徳的な気持ちに襲われていた。