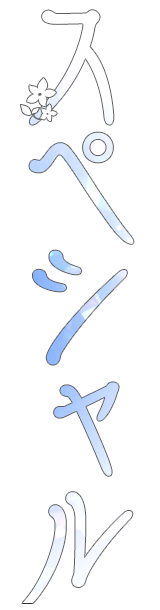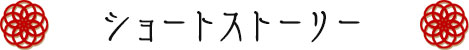「……ねぇ、縁。変なことを尋ねてみてもいいかな」
「どうぞ」
「この島でみんなが言う『交配』ってさ、その……その、つまり……そういうことだよね」
「閨を共にするということだね」
「やっぱりそうだよね!」
僕は思わず、湯船の中から身を乗り出してしまった。
「暴れると湯が溢れますよ、お客様」
「ご、ごめん! せっかくの薬湯が……」
黄泉の死菫城は、その人の病にあわせた薬湯を使わせてくれることで有名だ。主であるこの縁が、そういったものに詳しいらしい。
「日本では……そういう言い方はしなかったから、念のため確かめたかったんだ」
「オランピアと交配したいの?」
「縁!?」
僕はまた立ち上がってしまい、大量の湯が溢れ出た。
「やり方は分かる? 不安があるなら相談に乗るよ」
事も無げに彼はそう口にし、湯船に湯を注ぎ足す。
「か、からかわないでくれる!? 僕はそんな不埒なことを考えてな……」
「でもそれが彼女の役目だよ、時貞」
穏やかで柔らかで、いつも通りの口調だった。
「彼女はたった一人の【白】……故に夫となる者を定め、交配し、次の【白】を産まなければならない。花婿捜しはそういうことだよ。時貞だって本当は分かってるだろ?」
どう答えていいか分からなくなり、僕はゆっくりと湯の中に身を沈めた。『私、この天供島に少々不満があるの。だから少しでも変えたいと思って』
【白】のオランピアは誰とも口を聞かず、誰とも目を合わせない。島の皆はそう言う。【黄】の道摩の元で暮らしているくらいだから、お高くとまっているのかも知れない───そう思っていたのに。
『……美味しい! 中にも胡桃がいっぱい!』
初めて言葉を交わしたあの日、彼女は本当に嬉しそうに蒸かしたての饅頭を頬張っていた。その上、僕が飼っている白鼠パリスの兄が迷子になっていたところを助けたらしくて、ちっとも評判通りじゃなかった。
「……あのさ、縁。また変なことを尋ねてみてもいいかな」
「どうぞ」
「女性はさ、そういう……そういうことに巧みな男が好きなのかな。ほら、みんなよく話すじゃないか。色里でこれだけ相手を悦ばせたとかさ、何人もの女性と閨を共にしたとかさ、やり方とか……沢山……」
「なら時貞はさ、彼女がそういう男を好きだと思うの?」
今度は湯船の中で滑りそうになり、慌てて端にしがみついた。
「お姉さんは……純粋だよね」
「純粋だね」
「僕とだってあんなに簡単に『仲良くなりましょ!』なんて言ってさ」
「でも、言われて嬉しかったろ?」
言葉につまり、僕は縁を眺めた。お姉さん───彼女の周囲には素晴らしい男性が沢山いる。朱砂は上位の【赤】で、顔もよくて背丈もあって、しかもコトワリの所長で、玄葉だって副所長で優秀な医師で、縁だってこんな豪華な店の主で、女性が喜びそうなことを沢山知ってる。
それに比べて、僕は何もない。
この島に流れ着いた、余所者だ。
人に誇れるようなことは何もしていない。
「……ねぇ、縁。また変なこと言うけど……もし、もしもだよ? 仮に、仮にの話だからお姉さんには絶対、内緒にしておいて欲しいんだけど、万が一そんなことになったとしても……僕は上手く出来る思う?」
「なら誰かで練習しておく? 年下の男の子と遊びたいご婦人なら心当たりがあるよ」
「そんなのは嫌だよ!」
「なら頑張るんだね」
縁は微笑んで、特製ぬか袋を手渡してくれた。それを受け取り、僕は首筋をそっとなぞる。
「……ねぇ、縁。真っ暗闇にしておけば……いいかな。それともやっぱり僕なんかが……お姉さんと交配なんて……望んではいけないかな」
「君が本当に彼女の半身なら、アマテラス様が味方してくれるよ」
───『アマテラス様』。天女島に眠るというその女神様なら、余所者の僕でも救済ってくれるのだろうか。
「……ごめんなさい、重いでしょう」
「だからこれくらい平気だって。それって僕を非力だと馬鹿にしてるってことだよ?」
今日は二人で滝を見に出かけた。所謂、この島でいう『デート』のつもりだった。そこで彼女は足に怪我をしてしまい、馬車が拾えるところまで背負うことにしたのだ。島原にいた時、傷つき倒れた者や、骸さえ背負って運んだ。命絶えた者はひどく重い。だから彼女くらいなら余裕だ、なんて思っていたのに。
ちっとも重くはなかった。彼女の躯は柔らかくて細い。でも僕の首筋にずっと微かな吐息が触れるし、耳元で楽しげな声が聞こえるしで、どうしていいか分からなくなる。
『私、この天供島に少々不満があるの。だから少しでも変えたいと思って』
あの日の彼女の眼差しが、僕の奥まで突き刺さった。
だから僕は、変えたい。
成し遂げたい、この島のみんなから、お姉さんから認められるように。
朱砂も玄葉も縁も大好きで、尊敬している。でも負けたくない。花婿に選ばれたい、選んで欲しい。
島には、不思議な言い伝えがある。
───その昔、かたちのない神が自らの霊玉を二つに分かち、男と女を作った。それ以来、人は魂の半身を失った状態で産まれることになり、互いの対となる相手を捜し求める運命となった。故に人はその半身に巡り逢うと、恋しさの余り片時も離れられなくなるという。
片時も離れられない、なんて。
島に流れ着いてそれを聞いた時には大袈裟な昔話だと思ったのに、今はそれが嘘ではないのだと感じている。
お姉さんと離れたくない。
お姉さんの半身でありたい。
必死にそう願っても、僕はまだ何も成し得ていない。
ああ、我が主よ。
貴方様の尊い御声はいつ私に───届くのでしょうか。