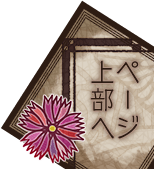- 久世ツグミ
-
「ここを通るのは久し振り。独りだとやっぱり少し怖くて。
近道なのは分かるのだけれど」
- 星川翡翠
-
「不気味と言えば不気味ですよね。
僕は慣れてしまったので急いでいる時とか、雨の日は使います」
- 久世ツグミ
- 「雨の日! 確かにそれはいいか……きゃぁっ!?」
- 星川翡翠
- 「危ない!! あ……うわぁっ!?」
- 久世ツグミ
- 「きゃ……!?」
- 久世ツグミ
- 「……!?」
- 星川翡翠
- 「あ……っ」
- 久世ツグミ
- 「ご、ごめんなさ……っ」
咄嗟に躯を離そうとしたものの、その背中を
思い掛けず強い力で押さえ込まれた。
- 久世ツグミ
- 「……翡翠?」
- 星川翡翠
- 「……駄目です」
そう言った翡翠の眼差しは、先刻のそれとは違っていた。
ランプの、くすんだオレンジ色の光を映して
翠と紅の瞳が熱っぽく煌めいている。
- 久世ツグミ
- 「あ、あの……翡翠……っ」
- 星川翡翠
- 「……大丈夫です。僕は貴女を汚したりは……しない」
- 久世ツグミ
- (……汚したりはしないと言うのは……)
その言葉の意味を考えようとして、
私は自分を恥じた。
そんな私の髪に翡翠の指がそっと絡む。
この間、本を開いてしまって心配された時よりも更に顔が近い。
- 星川翡翠
- 「……本当に、何も……しませんから」
誰かの顔をこんな近くで見たのは初めてで、
恥ずかしさから力が抜けてしまいそうだ。
- 久世ツグミ
- 「……翡翠、あの……」
私達の唇はもう触れ合いそうな程に近く、
お互いの吐息をはっきりと感じる。
- 星川翡翠
- 「……もう少し、逃げないで下さい」