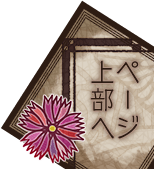どうすればいいのか分からなかった。
ただ少なくともはっきりしていることがある。
もう私は───彼に必要とされないということ。
- 鷺澤累
- 「…………」
私はやっとの思いで立ち上がり、彼から背を向けた。
部屋の扉はすぐそこなのに、まるで逃げ水のようにひどく遠く思える。
- 久世ツグミ
- (……私はもう……離れるしか出来ないの……?
私が出来ることは……もう何も……)
振り返る勇気もなく、おそるおそる扉のノブに
手を掛けようとした時だった。
- 鷺澤累
- 「……駄目だ……!!」
- 久世ツグミ
- 「!?」
- 鷺澤累
- 「……駄目だ……僕の前から……いなくならないでくれ……っ」
- 久世ツグミ
- 「……累……っ」
- 鷺澤累
- 「……ごめん……っ」
- 鷺澤累
- 「ごめん、ごめん、ごめ……っ」